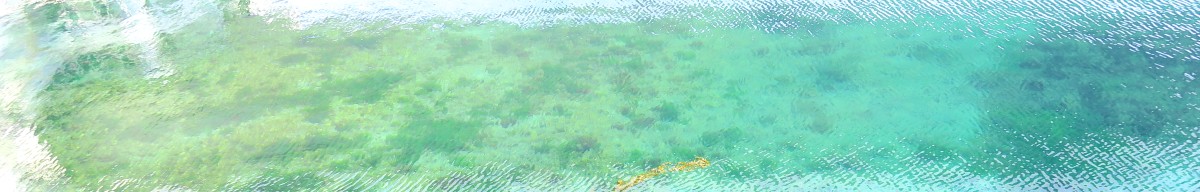こんなリクエストをいただきました。
┌── ここから ────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
いつも心に染みる営業のお話ありがとうございます。
今週のブログの少し前の「売りのプレッシャーをコントロールする」を拝見して、
・「売りのプレッシャー」は害悪であるかのようにとらえてはダメ
・エネルギーを閉じ込めてはダメ
・売りたい気持ちを抑えこんじゃダメなんです
と書いてあり、???となりました。
最近は売らない、押しつけない、お客様を傾聴する、というような営業本が非常に多く、だいたいの内容が売りのプレッシャーを隠すことを推奨しています。
吉見さんの実践で得た感覚的なものかと思いますので、文章化は難しいかも知れませんが、もしお時間があれば再度取り上げて下さると嬉しく存じます。(卸売業/浦和在住さん)
└── ここまで ────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
浦和在住さん、ありがとうございます。
営業チームを任されたときは、新人営業マンを連れて歩くことがよくありました。
私の隣に座らせてお客様とのやりとりを黙って見てもらうのですが、商談を終えて外に出たとたん「吉見さんは売りのプレッシャーがメチャメチャ強いですね」と言われることが多いんです。
それまで穏やかに話していた私が、次第に語気を強めて、一気にプレッシャーをかけるのが私のクロージングです。
確かに強い。
ガツンと言い放って無言の圧力をかけます。
あきれるほどワンパターンなんですよね。
–
営業トークの研修で一番よく質問されるのがクロージングです。
私がクロージングでどんなトークを使っているのかを知りたいと。
もちろん包み隠さず教えます。
隠さず、というか……。
私のクロージングはひとことしか言わないので隠しようがない (^_^;
これだけです。
「ここで決めてください」
そして相手が答えを出すまで動かない。
シンプルでしょう?
でもあなたはこのひとことが言えますか?
それにしても、なぜ相手はこのひとことで決めてくれるのでしょうか?
–
商談にはザックリと大きく分けてふたつのステップがあります。
ひとつは相手の現状を知ること。
これは本音を聞き出せないことには、どうにもなりません。
だから営業関連の本を開くと
・距離感を縮めなさい
・信頼関係を築きなさい
・質問は提案とセットで使いなさい
などの商談のテクニックが詳しく紹介されています。
では、ふたつめは?
ここから先が営業の仕事になります。
相手の状況を把握したら、自社の製品でどれくらい相手を変えることができるのかを予測します。
・本当に自社の製品が一番ふさわしいのか
・確実に効果を発揮できるのか
・機能が不足していないか
・オーバースペックではないのか
・投資した金額を回収できるのか
プロの視点で判断すること。
相手の現状を把握して、プロが最適な商品を選択して提供する。
この自信がないのなら営業をやめなさい。ただのモノ売りになってしまう。
相手の未来を創るのが営業の仕事です。
「売れればいいや」なんて気持ちで売り込みにこられたら、相手はいい迷惑です。
しかし、相手にとってプラスになる と確信を得たら、相手のために本気で売り込んでください。
プロが厳選した商品を勧めてください。
迷わずプレッシャーをかけてください。
–
これを使えば効果が期待できるとわかった相手は、あなたから買わなくても、いずれどこかで買います。
そのとき、安物を買って失敗するか、ムダに高すぎる商品を買うか。
プロのアドバイスがなければ失敗する確率が高い。
相手を失敗させてはいけません。
だから「これが最適です」ときっぱり断言してあげる。
「ここで決めてください」と売りのプレッシャーをかけてあげる。
そして、考えがまとまるまで、何も言わずに待つ。
これがクロージングです。
–
相手が信頼して本音で相談してくるまでは売りのプレッシャーをかけてはいけません。
相手の状況を把握したら、プロの目でしっかり選別して、相手にとって最善の商品を抽出 してください。
相手に失敗をさせないために、自信を持って本気でプレッシャーをかけてください。
このときあやふやな態度では、相手は決断できませんよ~!
相手に失敗をさせないために 「ここで決めてください」とキッパリ言い切る。
「売りのプレッシャー」は 相手のために使うもの。
害悪ではありません。
ー 撮影場所と機材 ー
横浜
OLYMPUS PEN Lite E-PL5
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6

市場の創造は本当におもしろい仕事です。
一緒に挑戦しましょう!
吉見 範一(よしみ のりかず)
最新記事 by 吉見 範一(よしみ のりかず) (全て見る)
- 売れないバンドマン、営業所に迷い込む - 2025年8月13日
- 営業は量子物理学より難しい? アインシュタインに学ぶ営業の真髄 - 2025年8月9日
- 【実体験】マンネリを打破した、私の仕事の選び方 - 2025年8月3日